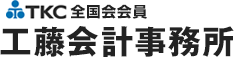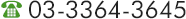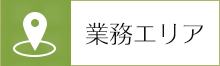平成29年より国税(所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税などほぼ全ての国税)をクレジットカードで納付することが出来るようになりました。
1.納付の方法
インターネットで「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスし、納付税目・税額・カード情報などを
入力して納付。
2.利用可能なクレジット
Visa,Mastercard,JCB,American Express,Diners Club,
TS CUBIC CARD
3.決済手数料
決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税
別)を加算した金額となります。
4.クレジットカードのポイントは付くのか
クレジットカードのポイントについてはカード会社の会員規約に基づきます。
5.クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合
法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において納付手続きを完了していれば、クレジット
カード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。
6.クレジットカード利用代金の支払回数は選べるか
お支払は一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中からお選びいただく
ことができます。
なお、分割払い又はリボ払いの場合は、利用額に応じた決済手数料に加えて、各カード会社の定める手数料
が発生する場合があります。
さらに細かい取り扱いは国税庁のホームページにQ&Aがありますのでそちらをご参照ください。
ポイントの付くクレジットカードであれば、決済手数料を支払ったとしても、クレジットカードで納付した方がお得になるケースが生じると思います。
法人設立・開業なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。